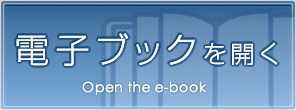hikarino_39 page 5/20
このページは hikarino_39 の電子ブックに掲載されている5ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
hikarino_39
HIKARI昨秋、附属図書館ラーニングコモンズにおいて、「国際デザイン思考ワークショップ-有田のこれからを探るー」を開催した。有田の窯元での合宿を含む5ヶ月間にわたるデザイン思考プログラムの中間報告会であったが、ラーニングコモンズという新たな知識共創の場づくりに挑戦する附属図書館行事としても位置づけられた。デザイン思考は、多様な専門領域・立場・文化を持つ人々の連携により、社NO会で求められる新たな価値を共創するための方法論である。今回も異なる特徴をもつ複数の窯元の経営者・非窯業の経営者・町議会議員・商工会議所・県内外の様々な職業の社会人、そして本学の学生や様々な分野の研究者ら36名が混成チームをつくり、デザイン思考を学び、その実践に取組んだ。自知識共創社会における図書館の役割佐賀大学デザイン思考研究所松前あかね治体・地域のクリエイティブコンソーシアム・民間投資家・本事業のスポンサーである米国領事館…多方面からの支援体制の中で育まれた「有田の0→1」の芽の幾つかは複数のファンドを獲得し、プログラム終了後も周囲の人々や組織を巻込みつつ、地域に根ざした当事者主導の自律的展開をみせている。文科省の国立大学第3期中期計画運営交付金配分の在り方検討会議事録においても「事業創造の核となる人材の育成」が朱字追記された。新時代を拓く事業共創、すなわち持続可能なイノベーション共創の方法論を実践的に学ぶ場は、学生の教育・社会人の学び直しの場であると同時に、イノベーション共創エコシステムとしての役割を直接的・間接的に果たす可能性を秘めている。「イノベーション」という言葉は浮いた印象を与えがちであるが、知識科学を開拓した野中らが「(その創出メカニズムを)暗黙知と形式知のダイナミックな相互変換運動」と説明するように、地に足のついた実践と深い知識を両輪とする。個々人が直接的な経験・共感を通じて対象から暗黙知を獲得し(共同化)、それを他者との対話や思索を通じて形式知化し(表出化)、得られた形式知を体系的にシステム化・理論化し組織知へと組み上げ(結合化)、組織知の実践・具現化を通じて個々人が新たな暗黙知を獲得し(内面化)、さらに新たな共同化へと循環させる、これこそイノベーション共創の方法論と言われるデザイン思考の本質である。私たちの社会が大きな転換期にある今、かつては効率的に機能した「与えられた課題に対して定石を適用し計画的に遂行する力」のみでは打開できない局面があふれている。近年の国内外での、特に我が国の産業界・教育界におけるデザイン思考の急速な普及は、ダイナミックな文脈の中で課題を自ら発見・定義し、その複合的な要素を包含する現代的課題に対して多様な人々と共に創造的な解を探り、柔軟に実践していくマネジメントが、かつてなく切実に求められている表れといえよう。そのような時代にあって図書館に期待される役割も自ずと変わり、従来のように個々人が形式知を獲得するための場としてのみならず、社会に開かれた知識共創の場としての役割が注目されつつある。本学附属図書館が様々な制約の下、既述のようなソフト面での知識共創の場づくりと表裏一体のものとしてラーニングコモンズ整備を捉え、進められていることに利用者として感謝したい。3